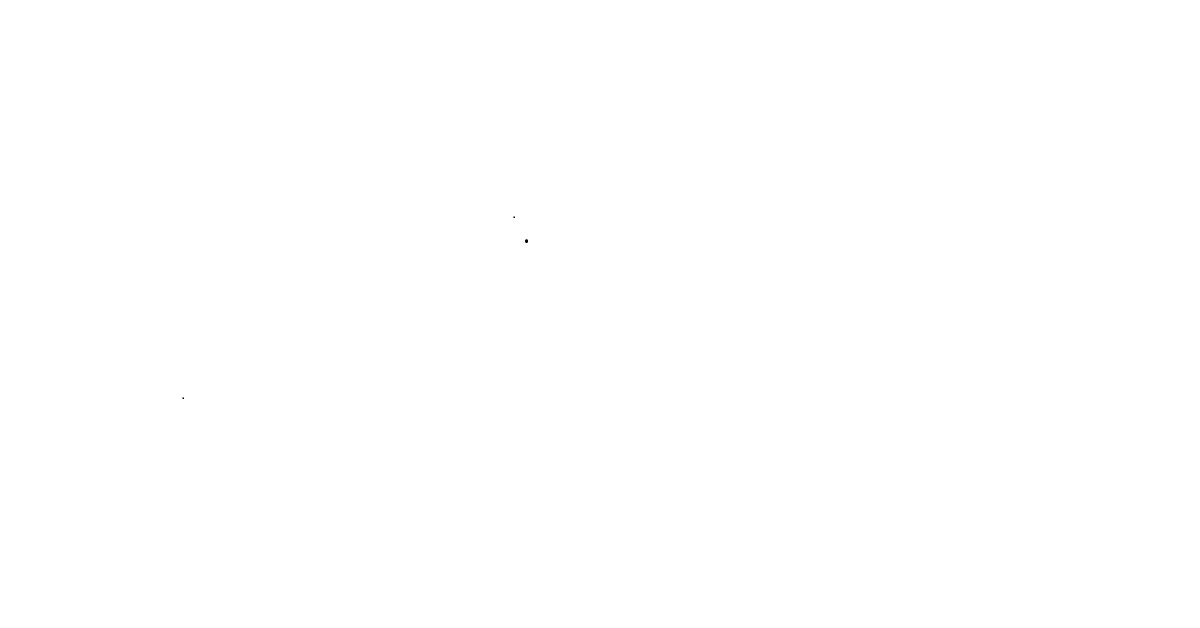「日本人と猫の関係は深い」とはよく言われるけれど、一体いつから猫は日本にいるのか?
猫が日本にやってきたのは、弥生時代後半(約2100年前) という説が有力だ。長崎県壱岐市のカラカミ遺跡で見つかった猫の骨が、日本最古の「飼われた」猫の証拠かもしれない。
しかし、それが「日本人と猫の付き合い」の始まりだったのだろうか?ここから、日本人と猫の関係がどう変化してきたのかを探ってみよう。
仏教とともにやってきた猫――奈良・平安時代
奈良時代~平安時代にかけて、中国から仏教の経典が持ち込まれた。その際、「ネズミから大切な経典を守るため」 に猫も一緒に連れてこられたという記録がある。
この頃の猫は、まだ特別な存在であり、貴族階級が飼う「珍しい動物」だった。例えば、『枕草子』や『源氏物語』にも猫が登場し、その優雅な振る舞いが描かれている。
庶民の暮らしへ――江戸時代の猫ブーム
時代が進み、江戸時代になると猫は庶民の生活に広く浸透していった。特に、町家ではネズミ退治のために猫の「放し飼い」が推奨されるようになった。
猫が店先に座ると「この店は繁盛する」という縁起の良いイメージも広がり、商人たちの間でも人気が高まった。浮世絵や民話にも猫が登場するようになり、徐々に「親しみやすい動物」としての地位を確立していったんだ。
現代の猫――ペットとしての新たな関係
明治以降、西洋文化が日本に入ってくると、「猫=ペット」という価値観が定着していった。
昭和・平成の時代には、猫は完全に家庭の一員となり、現在では「愛玩動物」としての立場が揺るぎないものとなった。
SNSの普及によって猫ブームが巻き起こり、多くの人々が猫の魅力を発信するようになった。
しかし、この変化の中で「猫は自由で気まま」というイメージが強まりすぎたとも言える。
本当に猫は自由なのか?それとも、私たち人間の目にそう映っているだけなのか?
日本人と猫の長い関係を振り返ると、猫と人間の「距離感の変化」が自由の概念にも影響を与えているのかもしれない。